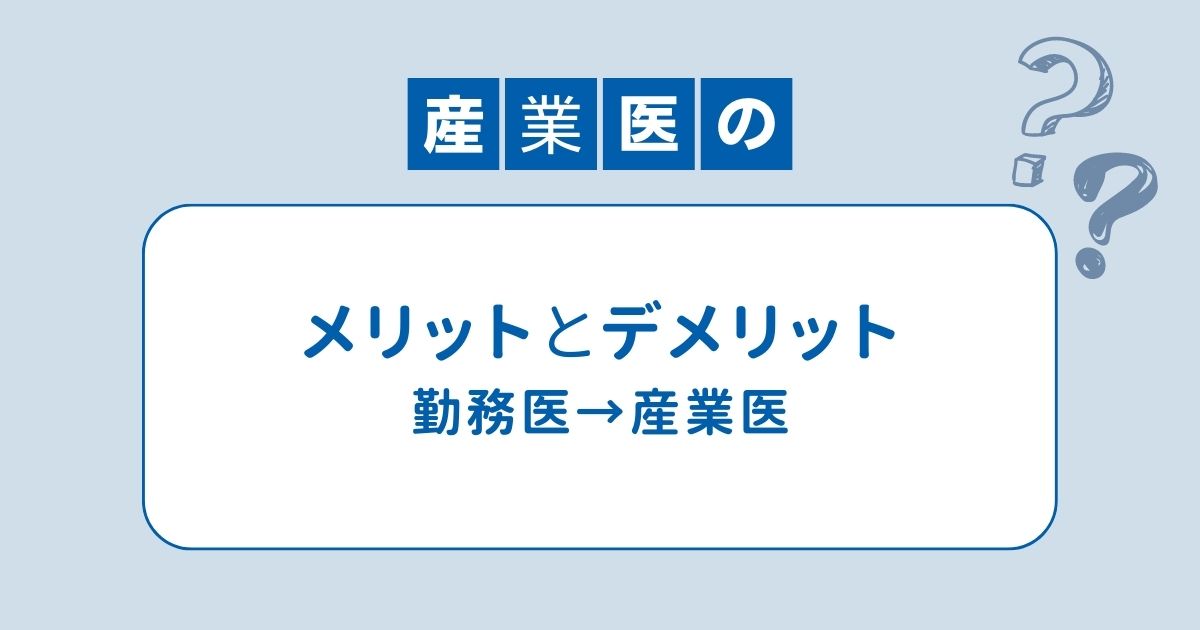産業医をやっておりますと、勤務医の友人からは「残業もなく定時で帰れるんでしょ?」「当直やオンコールもないし、土日祝日も休める。最高じゃない」と、若干の皮肉まじりに言われることもあったりします。
たしかにそうしたメリットは享受できているというのは否定しませんが、物事にはメリットもあれば、デメリットもあるものです。そこで今回は、「産業医になることでのメリット・デメリット」についてまとめてみたいと思いました。
これから産業医に転職しようとおられる、もしくは産業医の仕事に興味があるという方にとって、少しでもお役立ていただければ幸いです。
メリット1 QOMLはこの上なく良好
産業医になりますと、当然のことながら当直、オンコール、深夜呼び出しはありませんし、時間外の電話も本当に数えるほどです(それも昼~夕方のみです)。

でも詳しく書きましたが、常勤産業医になって一年目、一番の恩恵は「時間外の電話や呼び出しがない」と感じており、気兼ねなく晩酌もできれば、土日に出かけられることの喜びは格別なものでした。それまで臨床医時代に悩んだ不眠症もピタリとよくなり、体調も安定しています。


残業をしたことも本当に数えるほどで、社員さんとの面談が長引いたり、あるいは「どうしてもこの時間に面談をしていただきたくて…」と急遽、時間外に予定を入れられたりすることぐらいです。
この点、「とにかく勤務時間内はしっかり働くけど、時間外勤務は絶対にしたくない!」「当直、オンコールが苦痛」「土日は呼び出されることなくしっかり休みたい」といった方にとってはとても大きな恩恵を得られる就労条件だと思います。
メリット2 仕事を一通り覚えることに時間はかからない
あくまで「一通り仕事を覚えて、産業医としてなんとか業務を回せる」ということを想定して書きますが、その段階になるまで1年とかからないのではないかと、私としては思います。
臨床医であれば、当然数年、「医師10年目でやっと一人前」ということだと思いますが、産業医であればそこまでの年月は必要ないと思います。
具体的には、社員さんとの面談(健康相談、復職判定面談、高ストレス者面談、長時間勤務者面談など)や、安全衛生委員会への出席・講話、職場巡視、健康診断結果の判定業務など、臨床医をしておられた方にとってはそれほど苦もなく覚えられるのではないか、と思います。
もちろん、産業医として10年経験を積んでも、「ああ、あの判断は間違っていたな」と後悔したり、新たな発見・学びはまだまだあります。産業医として研鑽することは常に必要とはなると思いますが、「産業医として転職で困らないレベルで業務ができる」ようになるには、さほど難しくはないと思います。

メリット3 スケジュールに自由がきく
社員さんとの面談や、安全衛生委員会、子会社や関連会社訪問などのスケジュールはありますが、それ以外の時間はある程度、自由がききます。
そのため、「忙しくてランチもとれない」「トイレに自由に行けない…」といったことは避けられると思います。
少なくとも「忙しくて目が回りそうだ…」ということはほとんどありません(ごくたまに、長時間勤務者面談や高ストレス者面談がパンパンにスケジュールに入れられることもあったりしますが)。この点も、臨床医に比べてQOLMは高くなる要因だと思います。

メリット4 バイトしやすい環境
緊急での問い合わせや呼び出しがないということは、その分、バイトに集中できるということになります。特に「週4日勤務で、1日は丸々バイトにつかえる」「土日も気兼ねなくバイトできる」という環境は、勤務医の方々にはないことではないでしょうか。
実際、私は在宅でのオンライン診療を行っていますが、勤務医の先生方はシフトを入れても「同僚のヘルプで呼び出された」「同僚がコロナに感染して、当直を代わらざるを得なくなった」なんてことがあったりするようです。
その点、産業医は緊急での呼び出しもなければ、代わりに当直をしなければならないなんてこともありません。「バイトしやすい環境」というのもまた、産業医のメリットの一つであると思います。
メリット5 臨床医とは異なる分野だからこその利点
私は「臨床医に向いていない」と自分でも思っていましたし、面と向かって後期研修医時代に所属していた科の医長からも言われたことがあります。

「臨床医に向いていない」と思っておられるドクターにとっても、産業医は「臨床医とは異なる分野」と思ってやってみることができるのではないか、それもまたメリットの一つではないかと私としては思っております。
デメリット1 臨床医時代よりも不安定な雇用形態
産業医の雇用形態は、1年ごとに契約更新が必要な「嘱託契約」であることがほとんどです。よって、常勤産業医と言っても安定しているかと言うと、そうではありません。
この「嘱託」は正社員と異なり、あくまでも「業務を依頼する」という立場になります。嘱託契約で雇われている人と、正社員の大きな違いの一つが「一定期間限定で雇う」ということが明示されている点です。

私も一社目の企業で「契約更新をしない」と言い渡されているので、この不安定な立場であるということは身にしみて感じております。今もこの嘱託契約で雇われているわけですが、毎年、更新時期が近づくと「大丈夫かな…」と心配になります。
なお、一社目の契約打ち切り話につきましては、

に詳しく書いておりますので、ご興味ありましたらお読みいただければと思います。
当時の反省点を挙げるとするならば、契約更新をしてもらうためには、しっかりと(生殺与奪を握る)人事部を中心とした社員さんたちとコミュニケーションをとり、存在感を示す仕事をしなければならないということだと思います。
なお、「契約更新」を乗り越えるためには、次の記事

のように、
・「仕事をしているアピール」も大事(面談数の集計を行う、共有スケジュールにどのような仕事をしているかしっかり書き込む)
・「仕事を頼みやすい、相談しやすい」産業医になる。
・相談や問題をたらい回しにしない、「問題解決型」の産業医を目指す。
ということを心がける必要があると思います(自戒を込めて)。
デメリット2 臨床バイトの採用で不利になることも
特に産業医としての経験年数が長くなると、逆に「臨床バイトの採用で不利になる」ということもデメリットの一つです。
これは最近、私も非常勤の外来バイトを探す機会があったのですが、書類選考の段階で「産業医」ということで「本当に診療できるの?」と疑われ、落とされるということがありました。
面接に進んでも、やはり「どのような診療を今までしてきたのか、どんなことができるのか」という部分はかなり詳細に質問されました。現役で診療を続けている勤務医のドクターと、産業医として主に勤務している私だったら、やはり前者の方を採用したいという気持ちも分かります。
こうしたこともありますので、あらかじめ産業医になる前に長く続けられそうなバイト先を探しておくことも準備の一つとしてはやっておいた方がいいかもしれません。

デメリット3 太りやすい
産業医、特に常勤産業医になりますと、「太りやすくなる」ということはあると思います。病院勤務ですと、少なくとも外来、病棟など院内での移動があり、座りっぱなしのデスクワークということはあまりないのではないでしょうか。
一方、産業医ですと基本的には「社員さんとの面談」などが主な仕事となり、近距離の会議室とデスクの行き来のみの移動となってしまいます。支社・関連会社への訪問がある場合もありますが、基本はデスクワークが主体となります。消費カロリーが少なくなり、運動習慣がないとすぐに太ってしまう可能性は高いです。
また私を含めお酒好きな方は、晩酌も要注意です。時間外の呼び出しやオンコール、当直もないため、下手をすると「毎晩飲んでしまう」なんてこともあります。結果、食べる、飲む量が増えて摂取カロリーも増え、これも肥満の原因となってしまいます。
デメリット4 コミュ障には辛い部分も
「コミュ障には辛い部分もある」ということが挙げられます。私も人見知りでなかなか積極的にコミュニケーションをとれる方ではありませんので、この点は「ちょっと大変だよなぁ…」と思う点です。
社員さんとの面談を踏まえ、あまり日頃から接点のない人を含め、関係各所にその内容を伝えたり、就業制限で必要な相談をしたりと、自分からコミュニケーションをとる必要があります。
このあたり、人によっては「なんだそんなこと?」「それは勤務医でも必要なことじゃないか」と思われるかもしれませんが、そうしたことが不得手としている人間からしますと、一呼吸おいて、「これは仕事なんだ。コミュニケーションをとる必要があるんだ」と自分に言い聞かせることも必要があったりして、若干のストレスを感じるところではあります。

デメリット5 「合わない」人にはとことん合わない
特に臨床医としての未練が強く残るようなタイプの方に多いと思いますが、産業医の仕事が「合わない」という方はたしかに一定数いらっしゃると思います。

社員さんとの面談や、書類作成、健康診断の判定業務など、「退屈で合わない…臨床医の方がよかった」と思われる可能性はどうしてもあります。この点、やはりやってみなければ分からないというところです。
一つのチェックポイントとしては、認定産業医の資格取得の際、講座・研修を受けられたかと思いますが、あれで「退屈でほとんど聞いてなかったよ」ということだとやめておいたほうがいいと思います。
以上です。
メリット、デメリットはそれぞれありますが、私は産業医は興味深く、やりがいのある仕事であると思っています。もちろん、辛いこともたまにはあったりしますが、大部分は楽しめています。
もし「産業医、興味あるな。やってみたいな」ということでしたら、ぜひ転職をしてみることをオススメしたいと思います。ただ、初めてですと「転職ってどうやるのよ」と分からないことだらけだと思います。
私は3回の転職すべてで、リクルートドクターズキャリアにお世話になっており、毎回内定をいただいています。もしご興味がありましたら、こちらの転職エージェントにまずはご相談をしてみてはいかがでしょうか。