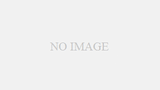産業医面談を行っておりますと、相談に来られた社員さんから「異動したいんです。どうにかなりませんか?」という相談されることもあります。
さらに一歩踏み込んで、通院中の精神科のクリニックや病院で、「配置転換が望ましい」といった診断書を書いてもらって、持参してこられる社員さんもいます。また、産業医自身が意見書で、「配置転換が望ましい」と記すこともあります。
ですが、異動したい社員さんたちが気になるのは、「それで本当に異動できるのか?」というところではないでしょうか。
そこで今回は、産業医の「配置転換が望ましい」という意見書の効力について書いてみたいと思います。
「配置転換が望ましい」の法的拘束力
そもそもこの意見書の法的拘束力、もっと言えば「産業医の意見」の法的拘束力を考えた場合、これは安衛法第13条3、4に基づきます。
3.産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4.事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
この文言からすると、あくまでも「勧告」であり、企業側は「尊重しなければならない」とはありますが、「何がなんでも従わなくてはならない」という強制力はないということになります。

「ないよりはあった方が異動しやすい」という後押しにはなるかな、と思います。ただ、最終的な決定権は会社側にあるということは変わりません。
企業が異動させる場合/させない場合の違い
では、この「配置転換が望ましい」という意見についてですが、企業側が了承する時と、しない時、どのような違いがあるのでしょうか?
この点は、私見ですが「勤続年数」や「社員自身の役割・働き・適性」に大きく関わってくるのかな、と思われます。
やはり入職間もなくで「この部署は自分には合わない」といったことでは、なかなか意見が通らないということもあると思います。逆に、「ウチの会社では合わないようだね」と、やんわり退職を促されてしまう可能性もあったりします。
また、専門知識・経験を見込み、その働きを期待して中途採用をした人であった場合、それは「異動を」ということになりにくいと思います。管理職採用の場合であっても同様だと思われます。
一方、ある程度の勤続年数があり、それなりの働きをしてきた社員での場合、「配置転換」は通る可能性が高いように思います。というのも、それなりの結果を出してきた人ですので、異動先でも「よく働いてくれそうだな」と人事側も判断するわけです。
また、当然ながら「異動してパフォーマンスを発揮できる適性があるのか」ということもありますので、この点も会社側は判断して考えるはずです。
このような違いがあって、「配置転換が望ましい」という言葉を企業側は対応を異にするように思われます。ですので、産業医面談で「異動をしたい」と訴えた場合でも、結局のところ判断するのは企業ですので、産業医が後押しをしたところで拒否されるケースはあると思っていただいた方がよろしいかと思われます。
「配置転換に関する意見書」を書かない産業医
「配置転換に関する意見書」を書く/書かない、といった判断基準は産業医によっても異なると思います。実際、私の場合は「配置転換が望ましい」という内容の意見書はできる限り書かないようにしています。
その代わり、「異動したい理由を伝えた上で、人事面談をしてもらうように申し入れしましょうか」と提案します。人事側に話を聞いてもらい、その上で異動可能かどうかを実際に判断してもらうわけです。

ご自身の思っていること、伝えたいことを人事面談で実際にお話しできる場を設けるという意味でも、「意見書で一方的に通達するよりも、人事面談をしてもらう」という方がいいのかな、と私としては思います。
異動するために必要なこと
産業医として、今までのケースを見てきた経験則ではありますが、人事側が「単なるわがまま」か「まっとうな理由だ」と判断するかで処遇が変わっているように思います。
というのも、「異動希望」を全てかなえていたら、それは会社は回らなくなるわけで、「今の部署が合わないから」というだけでは、なかなか異動はできないと思われます。
異動できたケースで言うと、「パワハラだとは言えないまでも、上司が原因でバタバタと前任者が休職に追い込まれている部署」で、目下、体調不良を訴えているような人がいた場合、「これはまずいぞ…」と人事側も判断して異動させたということもあります。
前提として「真面目に、ひたむきに今まで仕事をしてきている」という評価があり、なおかつ「それは異動したいと言い出しても仕方ないね」という理由があった場合には、異動希望が通っている印象です。
人事面談に臨む上でやっておくべきこと
人事面談は、「ここが希望の部署です。異動させてください」「はい、そうですか」というわけにはやはりいきません。人事面談での話を上手く運ぶためには、以下の点をしっかりとまとめて臨むことをおすすめします。
・今までどのような経緯や原因があって、異動を望むのか。
・希望の部署はどこか(できれば第一、第二、第三希望まで)。
・希望の部署に異動する上で、自分の適性・知識・経験がどのように活かせるか。
ということをあらかじめまとめておきましょう。「その場ですぐ答える」というのはなかなか難しいので、できればポイントをスマホのメモなどに残しておき、直前に見ておくとよろしいかと思います。