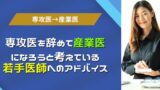私自身、内科系の後期研修医から産業医になる上で、戸惑ったことがありました。後期研修医ですと、入院患者さんの診療と外来・救急当番、カンファレンスの準備など「やらなければならない仕事」というのは結構なボリュームでした。
そうした仕事量、業務負荷に慣れていていきなり産業医になると、もしかしたら「あれ?」と戸惑うかもしれません。というのも、勤務医と産業医ではやはり仕事の量やその負荷が異なるケースが多いからです。
そして、その違いを踏まえた上で、特に若手医師が産業医になったようなケースでは、注意すべき問題があると思っています。今回は、そうした臨床医と産業医の違いについて書いてみたいと思います。
産業医の業務負荷
面談の件数も日によって異なりますが、「1日、朝から晩までびっしり」なんてことはない(企業によってはあるのかもしれませんが)ですし、健診の判定業務などもそれほど社員数が多くないところですと「健診のシーズンに数日~何週間実施する」という感じだと思います。
「今日は1件面談をして、安全衛生委員会の講話資料を作成しただけだった」という日もあったりします。こうした状況が続いていくと、もしかしたら「ヒマだなぁ」と感じてしまうこともあるかもしれません。

業務負荷の調節
中高年医師になってきますと、そうしたゆったりとした産業医の業務ペース、負荷にもペースを合わせるということも最初からできるかもしれません。ですが、若手医師だとそうしたことが難しいということもあると思います。

では、そこでどうするかと言えば、「バイトで調節をする」というのも一つの手であると思います。平日の1日を使った外来バイトや、土曜などで当直バイトを入れるのもいいでしょう。また、こうした臨床バイトを続けることで、経済的にももちろんプラスになりますし、「臨床の勘を鈍らせない」こともできるというメリットもあります。
働き方の自由度の高さ
ベースとなる仕事の負荷が高すぎないというのは、逆に言えばそこから高くすることも、そしてそれに疲れたら「ゆるく働く」ということもできるわけです。
この自由度の高さは、産業医という仕事の大きな特徴であるとも言えます。私の場合、非常勤バイト1日、そして平日の空き時間に自宅でオンライン診療バイトを夕~夜診で行っています。
ちなみに、私がリクルートドクターズキャリア[PR]に常勤産業医の求人紹介を依頼した時には、非常勤バイトの求人も併せて紹介してもらいました。もしこれから産業医に転職を、とお考えでしたら、同様にバイト紹介も依頼してみてはいかがでしょうか。